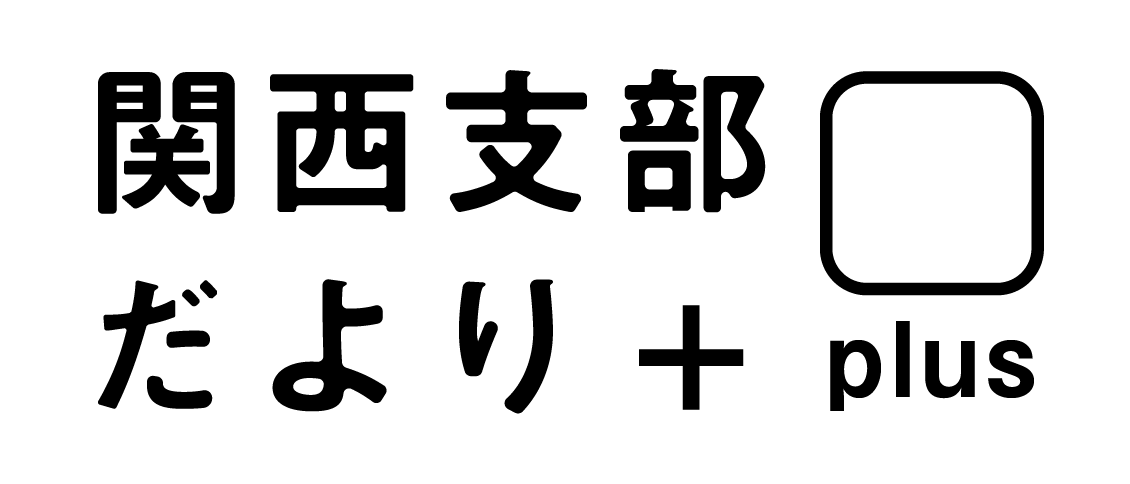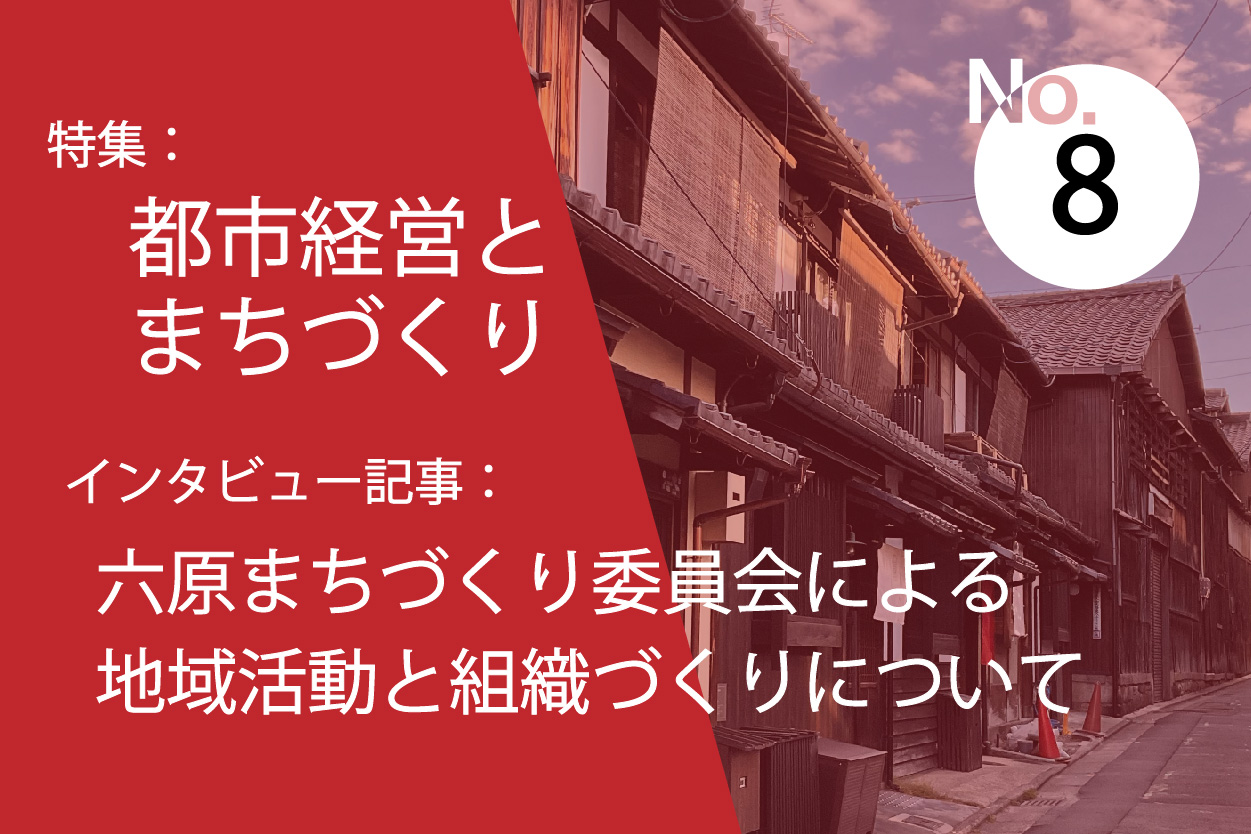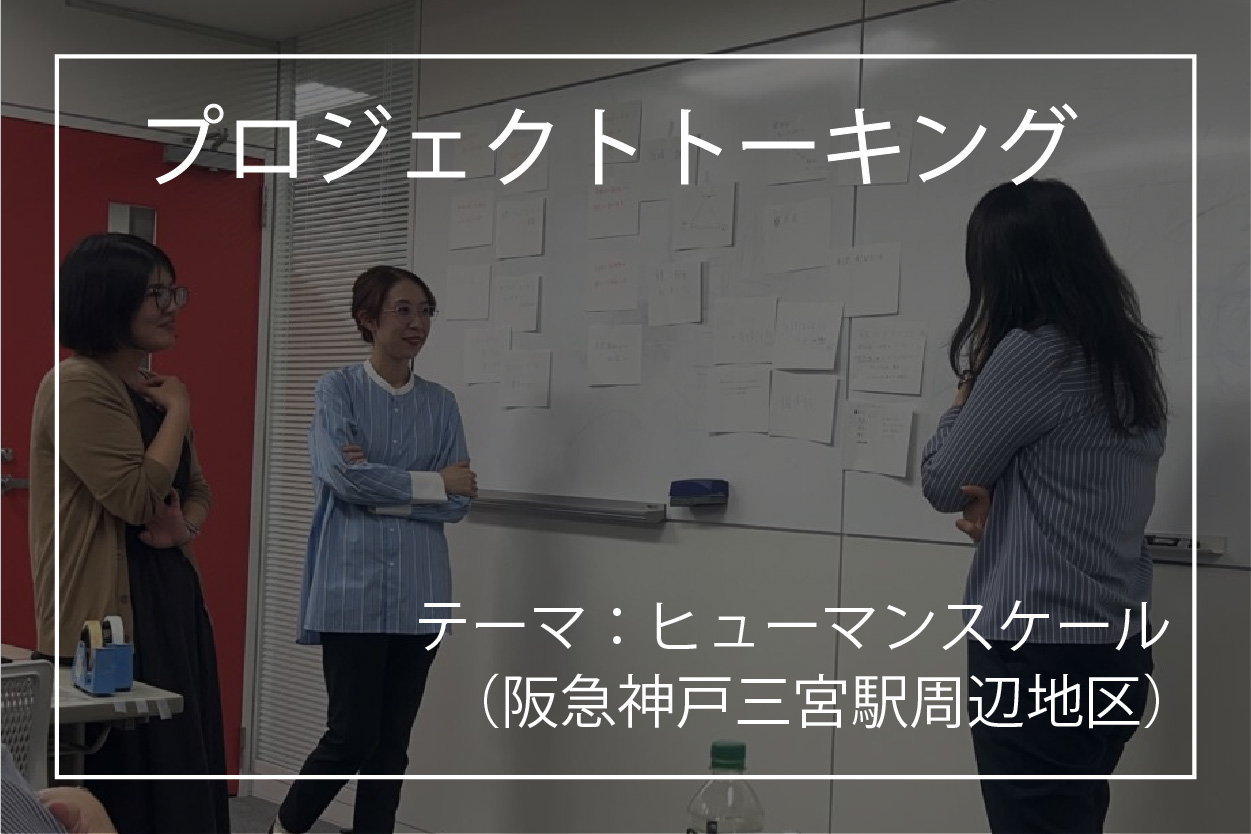関西支部だより+ 37号(2024年1月版) 特集「都市経営とまちづくり」No.8
インタビュー記事菅谷幸弘さん(六原まちづくり委員会委員長)、小林悟さん(六原まちづくり委員会・(株)スマート・ホーム)
日時:2023年9月25日 場所:東山区六原学区やすらぎ・ふれあい館
主催:都市計画学会関西支部編集広報委員会
趣旨:京都市六原元学区において、防災まちづくり・空き家の予防・再生に取り組まれている六原まちづくり委員会の菅谷幸弘さんと小林悟さんに、まちづくりの取り組み内容や組織づくりのポイントついてお聞きしました。

六原元学区の現況
菅谷氏:私たちは「住んでいてよかったなと思えるまち」、「これからも住み続けたいまち」を目標に活動をしております。六原まちづくり委員会は地域住民が半数、外部の方が半数という構図になっています。そして、男女比も半々です。六原元学区は京都駅が徒歩圏になります。清水寺などの観光地が周辺にありますが、六原元学区内にはたいした観光施設はなく、住居エリアになっています。高齢化率は32.3%ですが、かなり高い方になります。空き家率は12.9%です。六原まちづくり委員会ができた当初の空き家率は14%ほどでしたので若干減少しています。京都市全体でも減少傾向にありますが、六原元学区は京都市の水準よりも若干高い状況にあります。
菅谷氏:今後、高齢化や人口減少により地域力の低下が予想されます。町内会自体がもう活動できないというところも出てきている現状にあります。六原元学区のまち並みについてですが、周囲には五条通などの広幅員の道路がありますが、地域の中に入っていくと非常に狭い道が多くあります。約100本近く路地があると言われており、幅員1.1メートル程度の路地が多いです。トンネル路地も散見されます。


不法駐車をなくすために、以前は囲いをしていましたが京都大学の学生等に関わってもらい、このように雨庭として再生しました。掃除や草むしりも町内でやってもらっています。(菅谷氏)
六原まちづくり委員会での活動内容
菅谷氏:私たちの活動は、行政事業から始まり、今では地域に移行し、地域主体で活動しています。活動費用は自治連合会からではなく、東山区のまちづくり支援事業に申請することで費用を捻出しています。平成23年に六原まちづくり委員会が発足し、防災のまちづくりに取り組んできました。また、平成26~27年ごろには民泊が急増したため、龍谷大学の阿部ゼミナールのみなさんにもお手伝いいただき、民泊問題への対応について冊子でまとめるなどの活動を行ってきました。

右写真:新型コロナウイルスの影響以前はペンシル型の簡易宿所であった。現在は売り物件となっている。

菅谷氏:具体的な活動内容についてですが、「空き家・高齢者対策」について説明します。かつては空き家問題と高齢者対策は別々で取り組んでいましたが、空き家問題は高齢者対策とリンクしていることから別々で対応するよりも一緒に取り組んだほうが効率がいいだろうということで、今では一緒に取り組んでいます。行政事業として空き家の物件調査に取り組んだ際は、コンサルタントや企業がついているのでスピード感をもって成果を上げられました。しかし私たちだけで成果を追い求めると成果が出ない疲弊感で、やる気が失せてしまうような心境に陥ったことがあります。この時に、専門家の先生から、「成果にこだわって取り組むよりも、まちの課題を見つめるような、持続可能な活動にしませんか」という提案をいただいて、すごく肩の荷が下りたことを覚えています。ですので、まちづくり委員会では大きな数値目標を立てずにゆるやかに取り組むようにしています。
菅谷氏:防災まちづくりの取り組みについては、路地に銘板を付けることで非常時に正確な位置を特定しやすくする取り組みを行いました。地域には約100の路地がありますが名前がついていませんでした。通り抜けができるものを「●●小路」、できないものを「●●路地」と名付けることで、非常時に通り抜け可能な避難路を特定しやすくなる効果があります。また、消防の指令センターにこの路地名が登録されたことで、「●●路地」と伝えるだけで緊急車両が駆けつけられるようになりました。実際に事例もありまして、消防署にも非常にわかりやすいと言われています。
菅谷氏:路地の名前を私たちまちづくり委員会で提案すると地域住民は反対するのではないかと思いました。ですので、そこにお住まいの方々に名前をつけていただきたいというお願いをしにいきました。路地の名前は様々です。例えば「笑い路地」という名前がありますが、「どうやってつけたんですか」と尋ねたら「私たちはいつも笑いながら生きていたい」ということで名付けられたそうです。

安全確保のためトンネル路地は耐震補強されている。
空き家活用・予防の取り組み
小林氏:空き家は地域の問題であると認識していますが、利活用がなかなか進まないのが現状です。空き家を貸すことや売ることに消極的なことが、空き家が長期化する要因となっています。このような活用する気がなく業者が入れない空き家は六原では約200軒程度ほどあります。私たちでも年に数件しか利活用できていないのが現状です。空き家になって手をつけると手間がかかり、所有者とコンタクトを取り、利活用するまで2~3年はかかります。このままでは空き家の発生スピードに対応できないので、空き家の予防に力を入れています。中でも啓発活動の一環で、読みやすい冊子を作成し地域の方にお配りしています。この冊子が好評で書籍化も実現したことでまちづくり活動の資金にもなりました。最近では、空き家の予防や利活用についてのショートムービー作成にも取り組んでいます。他にも、地域の方向けに、部屋の片付け、仏壇のしまい方などを題材として空き家の予防・利活用につながるセミナーを開催しています。
小林氏:私たちでは、20軒ほど空き家の利活用できていますが、年単位で取り組んでいるので活用件数は限られています。私たちは民泊にしたい、高く売りたい人はターゲットとはしていません。若い人に住んでほしいので、町内会に入ってもらえる人などを優先にマッチングしています。件数は求めていませんが、持続性を大切にして、楽しくやることを大切にしています。今後の展望としては、どのように空き家の予防をするかを検討しています。多くの家では、相続する手前で、所有者の健康寿命が尽きてしまうので、所有者が元気なうちに対策したいと考えています。そのため、健康寿命が尽きる前の60代前半をターゲットに、相続をもめないようにする方法などの「住まいの終活」の情報提供を考えています。そうした、もめごとを起こさないよう予防し、空き家状態が長期化しないようにする活動に今シフトしています。
編委:10年以上取り組まれていて、私が隣で見ていて思うのは徐々に地域の人を巻き込んで取り組むことが少しずつ広がって、認識も変わってきている気がします。空き家に関してやはり地域の人の共通の問題としての「空き家」という認識は深まっているという理解で良いでしょうか。それとも、そうはいってもなかなか認識は深まっていないのでショートムービーなどの啓発動画をつくったという話にも聞こえるのですが。
菅谷氏:空き家の所有者が地域に住んでおられる方だと非常に話がしやすいのですが、意外と遠隔地にお住まいの方がいらっしゃいます。地域外にお住まいの所有者に私たちの取り組んでいる温度にはなかなかなってもらえないという現実があります。
編委:空き家増加のスピードをなるべく抑えるという点についてですが、流通している空き家が少ないというところはなかなか地域で解決策を見いだすのは難しいかもしれないですが、このあたりは例えば小林さんのようなプロの方が入ってらっしゃることをうまく生かしながらという可能性はありますか。やはり住んでみたいという人は人生のどういうフェーズかはわかりませんが一定数いるだろうし、六原地域は地理的にもかなり良いところにあるので、そこもひとつ大きな問題かなと思います。
菅谷氏:ほぼあらゆる空き家に「この家売りませんか」と宿泊施設への転用を目的とした事業者がやってきます。それでもなお根強く残っているのが現在の空き家です。例えば住んでいる人に不動産屋がびっくりするような値段を提示してきて転居していった事例も多いです。そういった家は買い取られていきました。ある町内は借家が全部根こそぎ大家さんに売られてしまって立ち退かざるをえなかったというエリアもありました。だから7・8軒の借家が一気に無くなって住民もいなくなりました。「次どこに住めば良いのか。」と相談を受けたこともありますが、さすがにその対応は出来なくて「この地域に家はないか。」と聞かれたこともありますがなかなか紹介に至らなかったということで、でもやはりこの辺りに住み続けたいということで隣の学区にお住まいされている人もいます。再建築不可で路地に接していて、どう見積もっても本来坪単価20~30万円程度の不動産が、10坪強5000万円程度で取引された事例もあります。それくらい不動産が高騰している。五条通りも作家の家や陶器を売られている店が並んでいたのが今ほぼホテルに変わっています。路地に住んでいた人たちが転居せざるを得なくなった。それを見比べて歩いてもらうと地域の変化がよくわかります。

現在建設中の簡易宿所です。ここにも路地があったのですが。以前は手前に二軒家があり、その奥に借家がありましたが全部一斉に立ち退きされて、隙間にあった路地がなくなりました。(菅谷氏)
六原まちづくり委員会での活動体制・組織づくりのポイント
菅谷氏:私たちが住んでいるまちの中に横たわる問題というのは、例えば空き家問題とか高齢者問題、民泊問題もそうですが、「縦割り」でなく「横割り」で取り組まないと課題解決には結びつかないのではないかと考えています。ですので、六原まちづくり委員会は、各種団体から何名か出てきていただき、サポートしていただいています。縦割り組織にとらわれない横串で、問題解決を適材適所で取り組んでいます。
菅谷氏:地域でできないことは、外部の専門家の方々と一緒に取り組みます。専門家同士が関わることで解決できることもあります。これは六原のまちづくり委員会のある種の強みなのかなと思っています。地域の方をいかに巻き込むかも重要ですが、できるだけ「やりたい人」に声をかけずに、忙しそうな人に声をかけるようにしています。そういう意味では人を選んで関わってもらうことで人間関係に心を苦しめられるようなことがなく、問題の解決のためだけに活動できます。行政との付き合い方ですが行政にあれこれ要望する依存型ではなく、私たちは「ここまでは自分たちでやるが、この先は困っているので協力してほしい」といった相談型でお付き合いしています。
編委:住民主体で取り組むことでよりコミットできた課題などはありましたか。
菅谷氏:地域住民主体で問題解決に向けた取り組み行ってはいますが、とりあえず取り組みを続けていくことが大事であると思っています。ずっと走りっぱなしということはできないので、続けていくことがより重要であるのではないかと考えています。
編集広報委員:人間関係に影響されずに課題解決を実践されているところがポイントですか。
菅谷氏:どこの地域もそうだと思いますが自己主張の強い人が関わりだすと、声の大きい人の方向に流れる傾向があります。それが果たして、課題解決の方法に合ってるかどうかっというのはもう少し俯瞰して客観的に見ないといけないと思っています。必ずしも声の大きい人が正しい方向に導いているかというと決してそうではないのではないか。その時にコントロールする役割がどうしても大変だと思っていて、そういう労力を使わずして課題解決のために知恵を絞ることがベストだと思っています。