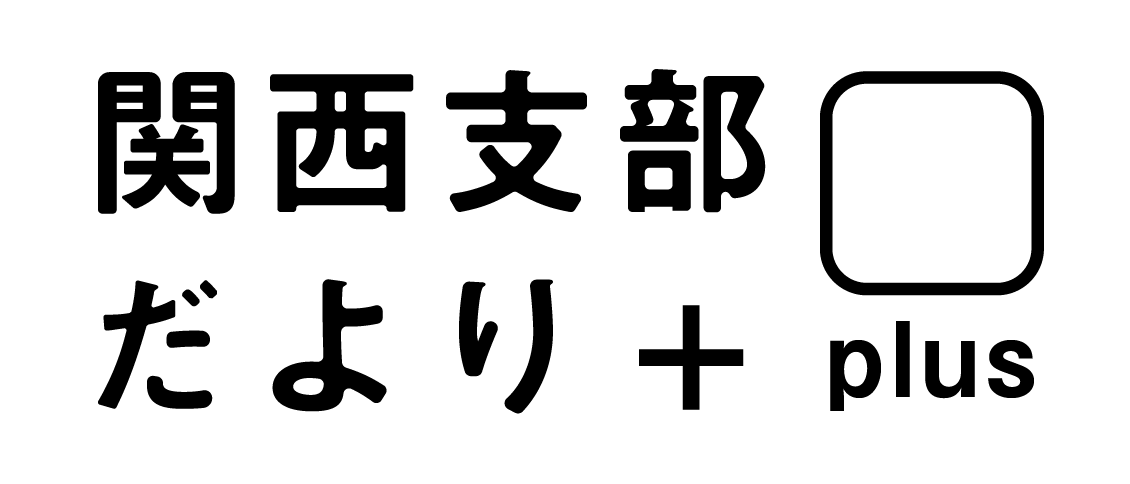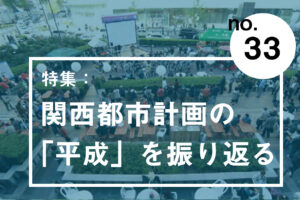
 2019年3月号
2019年3月号 支部長挨拶「関西都市計画の「平成」を振り返る」
_神戸芸術工科大学 小浦久子
平成は都市計画課題の転換期だった。...
平成は都市計画課題の転換期だった。...
 2019年3月号
2019年3月号 関西における平成期の国際輸送インフラ整備と運営
_神戸大学 竹林幹雄
本稿では平成期の関西の国際輸送インフラの 辿った歴史を振り返り、今後の輸送インフラの整備・運営と 関西のインフラ整備の今後を考えるための示唆を得ようとするものである。
本稿では平成期の関西の国際輸送インフラの 辿った歴史を振り返り、今後の輸送インフラの整備・運営と 関西のインフラ整備の今後を考えるための示唆を得ようとするものである。
 2019年3月号
2019年3月号 阪神 ・ 淡路大震災後の 「まちづくり」 の展開
_龍谷大学・石原凌河
本稿では復興検証・知識継承特別委員会での議論も踏まえながら、阪神・淡路大震災後のまちづくりの展開に与えた影響と、阪神・淡路大震災の教訓を次の世代に継承するための視点について述べていきたい。...
本稿では復興検証・知識継承特別委員会での議論も踏まえながら、阪神・淡路大震災後のまちづくりの展開に与えた影響と、阪神・淡路大震災の教訓を次の世代に継承するための視点について述べていきたい。...
 2019年3月号
2019年3月号 まちづくり三法から立地適正化計画までの中心市街地再生を巡る動向
_大阪大学・澤木昌典
「平成」は、商店街を中核とする中心市街地が、モータリゼーションによる郊外化と流通革命によって疲弊・衰退し、都市構造に大きな変革を生じた時代である。中心市街地活性化、都市再生が課題となり、都心回帰が...
「平成」は、商店街を中核とする中心市街地が、モータリゼーションによる郊外化と流通革命によって疲弊・衰退し、都市構造に大きな変革を生じた時代である。中心市街地活性化、都市再生が課題となり、都心回帰が...
 2019年3月号
2019年3月号 ニュータウンと住宅地開発の状況
_関西学院大学・角野幸博
ニュータウン開発の平成も、他の都市計画事象と同様に、バブル景気の崩壊や阪神淡路大震災の影響、少子高齢化の進展などによって、成長から成熟へと軸足を移す転換点を迎えた時期であった。そこで以下の5つの視点から平成を振り返ることにする。
ニュータウン開発の平成も、他の都市計画事象と同様に、バブル景気の崩壊や阪神淡路大震災の影響、少子高齢化の進展などによって、成長から成熟へと軸足を移す転換点を迎えた時期であった。そこで以下の5つの視点から平成を振り返ることにする。
 2019年3月号
2019年3月号 都市公園における官・民・市民協働の進展
_兵庫県立大学・赤澤宏樹
「協働」の時代への転換が、都市公園の管理運営を効率的にするに留まらず、市民・NPO・民間企業のノウハウや活力を社会に還元し、新たな都市サービス基盤として都市公園が機能する状況を生み出した。...
「協働」の時代への転換が、都市公園の管理運営を効率的にするに留まらず、市民・NPO・民間企業のノウハウや活力を社会に還元し、新たな都市サービス基盤として都市公園が機能する状況を生み出した。...
 2019年3月号
2019年3月号 平成時代の自転車交通と都市計画・まちづくり分野との連携の可能性
_大阪市立大学・吉田長裕
平成という時代は、交通分野において自転車交通が大きく見直された時代といってもいいのではないだろうか。環境や健康といった社会問題に対応するために、従来の自転車交通の位置づけを見直す動きは、国内外に...
平成という時代は、交通分野において自転車交通が大きく見直された時代といってもいいのではないだろうか。環境や健康といった社会問題に対応するために、従来の自転車交通の位置づけを見直す動きは、国内外に...
 2019年3月号
2019年3月号 都市の「余白」を取り戻すプレイスメイキングの潮流
_(有)ハートビートプラン・園田聡
平成の30年を都市デザイン・都市計画の視点から見つめ直すと、大きなテーマの1つに「つくる時代」から「つかう時代」へのシフトチェンジがあったように思う。都市空間においてもいかに付加価値をつけ他と差別化...
平成の30年を都市デザイン・都市計画の視点から見つめ直すと、大きなテーマの1つに「つくる時代」から「つかう時代」へのシフトチェンジがあったように思う。都市空間においてもいかに付加価値をつけ他と差別化...
 2019年3月号
2019年3月号 地域生態学への歩み
_大阪府立大学・上甫木昭春
昭和47年に大阪府立大学に入学した後、ランドスケープの領域でずっと過ごし、今年3月が定年退職となる。この間の「都市と私」をこれまでの仕事をもとに振り返ってみる。...
昭和47年に大阪府立大学に入学した後、ランドスケープの領域でずっと過ごし、今年3月が定年退職となる。この間の「都市と私」をこれまでの仕事をもとに振り返ってみる。...
 2019年3月号
2019年3月号 私の平成時代をふりかえってみた
_アルパック・坂井信行
私が社会人になったのが平成2年4月、“業界人”としてのキャリアも、ほぼ平成の幕開けとともに始まりました。それから早30年。30 年もやっていてその程度か、という叱責はもちろん甘んじて受けるつもりですが、私の平成時代をふりかえってみました。...
私が社会人になったのが平成2年4月、“業界人”としてのキャリアも、ほぼ平成の幕開けとともに始まりました。それから早30年。30 年もやっていてその程度か、という叱責はもちろん甘んじて受けるつもりですが、私の平成時代をふりかえってみました。...
 2019年3月号
2019年3月号 生野区桃谷に流れついて...
_建築家・桃谷のコミュニティ再生・住み開き・伊藤千春
桃谷に住みはじめて6年。桃谷がどこにあるのかも、生野区だということも分からなかった。そんな中始めたのが「momodani-project」。10年以上空き家だった1軒家を借りて、セルフリノベーションを始めた...
桃谷に住みはじめて6年。桃谷がどこにあるのかも、生野区だということも分からなかった。そんな中始めたのが「momodani-project」。10年以上空き家だった1軒家を借りて、セルフリノベーションを始めた...
 2019年3月号
2019年3月号 人とつながり、まちを楽しむ
_紀の川市地域おこし協力隊・新美真穂
私の暮らす和歌山県紀の川市は、フルーツのまち。私はここで、地域おこし協力隊として活動しています。一年を通して、さまざまなフルーツを収穫できることが自慢です。市内を歩けばそこかしこにフルーツ畑があり、桃の花が咲く桃源郷、真っ赤に染まる柿の葉、広がるイチジクの香りなど、...
私の暮らす和歌山県紀の川市は、フルーツのまち。私はここで、地域おこし協力隊として活動しています。一年を通して、さまざまなフルーツを収穫できることが自慢です。市内を歩けばそこかしこにフルーツ畑があり、桃の花が咲く桃源郷、真っ赤に染まる柿の葉、広がるイチジクの香りなど、...